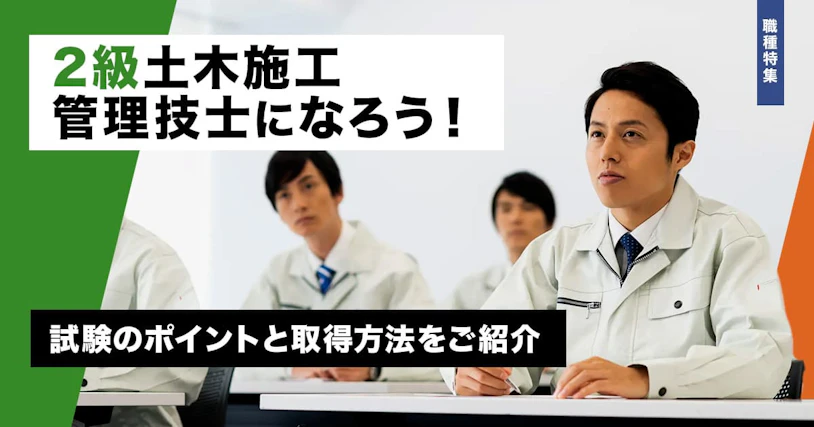
2級土木施工管理技士とは、建設現場における施工管理に必要な知識・技能を習得することを目的とした国家資格です。この資格を取得することで、建設現場の施工管理者として働くことができるようになります。
この記事では、2級土木施工管理技士試験のポイントや資格取得の方法について解説します。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社助太刀が運営する求人サイト「助太刀社員」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」が掲載されています。
理想の職場で新たな一歩を踏み出しませんか?求人詳細は以下をクリック!
2級土木施工管理技士の試験内容

試験内容
「2級土木施工管理技士」の資格は、「土木」、「鋼構造物塗装」、「薬液注入」の3つの領域に分けられています。それぞれの領域で合格した場合、その分野における「主任技術者」の資格を得ることができ、施工管理を行うことが可能になります。
試験は、第一次検定(学科試験)と第二次検定(筆記試験)の二段階で行われます。第一次検定は、以前の各種別別試験が廃止され、現在は共通試験として実施されています。試験科目は「土木工学等」、「施工管理法」、「法規」の3つで、全てマークシート方式の四肢択一形式の問題となっています。
新たな試験制度により、一度第一次検定に合格すれば、その後は第二次検定を受け直すだけで、他の2つの領域の資格も取得することが可能になりました。
しかし、試験の問題文は一貫性がなく、「名称を答えよ」、「正しいものはどれか?」、「誤っているものを答えよ」といった形で問われるため、必ず全ての問題文を最後まで落ち着いて読むことが大切です。これは正確な理解と適切な回答を可能にするための重要なステップです。
土木工学等
「土木工学等」の試験範囲は、土木一式工事の施工に必要な多岐にわたる専門知識をカバーしています。具体的には、土木工学だけでなく、電気工学、機械工学、建築学の各分野に関する基本的な知識も必要とされます。これらの知識は、工事現場でのさまざまな問題に対処し、適切な解決策を提供するために不可欠です。
さらに、試験では設計図書を正確に理解し、解釈する能力も求められます。これは、土木一式工事の施工管理を適切に行うために必要なスキルです。
施工管理法
施工管理法は、土木一式工事における、施工計画の作成方法や工程管理・品質管理・そのほか安全管理等工事の施工管理方法に関する知識を問う試験です。
例えば施工管理の基本方針や、施工計画立案の際の検討事項、施工計画のための事前調査など、施工管理を行うために必要な知識を問われます。
法規
法規では、建設業法や労働安全衛生法など、建設工事に直接影響を及ぼす可能性がある法令の理解が重要となります。これらの法律は、建設プロジェクトの全体的な計画立案から具体的な施工管理まで、様々な工程に影響を与える可能性があります。
また、これらの法令に基づく具体的な規則やガイドライン、ならびにそれらがどのように現場の施工管理に適用されるかについても理解する必要があります。これには、労働者の安全を確保する方法、環境保護に配慮した施工方法、質の高い工事を保証するための標準等が含まれます。
このような法令知識は、現場での施工管理を行う際に適法性を保つだけでなく、安全で品質の高い施工を実現するためにも不可欠です。
第二次検定
第二次検定は、試験者の具体的な施工経験を基にした記述式の問題です。問題の内容は、選択した種別により異なります。例えば、「土木」を選択した場合は土木施工管理法、「鋼構造物塗装」を選んだ場合は鋼構造物塗装施工管理法、「薬液注入」を選んだ場合は薬液注入施工管理法に関する問題が出題されます。
出題テーマは「品質管理」、「工程管理」、「安全管理」の三つのカテゴリから一つが選ばれます。このテーマに沿って自身の施工経験を記述し、どのように留意点を把握し、それをどのように管理したかを詳述します。
試験準備として、日常業務で得た経験や留意した点を手帳などに記録しておくことが推奨されます。これにより、具体的な事例や経験を思い出しやすくなり、それを試験で詳細に述べることができます。
また、第一次検定に合格すると、第二次検定を受けるための制限がありません。つまり、何回でも挑戦することが可能で、期間制限もありません。したがって、第一次検定に合格することがまずは目指すべき目標となります。
(参照:2級土木施工管理技術検定 https://www.jctc.jp/kentei/themes/tebiki2d0204.pdf)
2級土木施工管理技士の受験資格

2級土木施工管理技士の試験を受けるための資格は、学歴と実務経験によって定められています。
高度専門士の場合、指定学科を卒業してから1年以上の実務経験が必要です。もし指定学科以外を卒業した場合は、1年6ヶ月以上の実務経験が必要となります。
専門士の場合、指定学科を卒業してから2年以上、指定学科以外を卒業した場合は3年以上の実務経験が必要です。
高等学校、中等教育学校、専修学校の専門課程の卒業生は、指定学科を卒業してから3年以上、指定学科以外を卒業した場合は4年6ヶ月以上の実務経験が必要となります。
学歴不問の場合でも、8年以上の実務経験が求められます。
最終学歴や実務経験などについても影響がありますので、詳細を確認しておくことが重要です。また、年齢要件については、第1次検定のみを受ける受験者については、令和4年度の末日に17歳以上であることが求められます。これは平成18年4月1日以前に生まれた方が対象となります。
2級土木施工管理技士の試験スケジュール
2級土木施工管理技士の試験スケジュールは以下をご覧ください。

各申込用紙は1部600円で販売されています。第一次検定の申込用紙について、学校等からの一括請求は、当センターのみの販売となっています。
(参照:2級土木施工管理技術検定 https://www.jctc.jp/exam/doboku-2/)
試験難易度はどのくらい?合格率は?
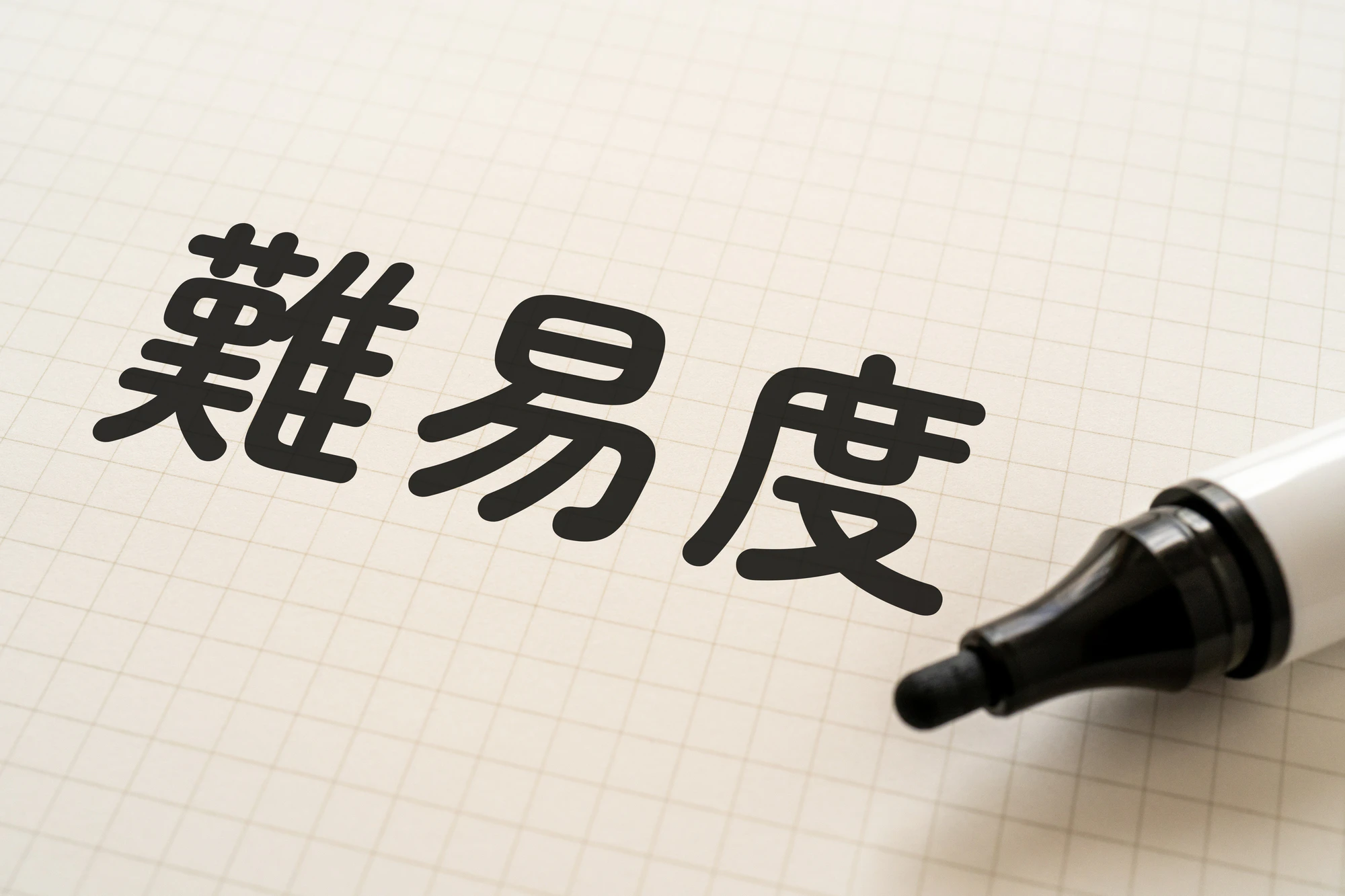
第一次検定の合格基準は、試験問題の60%以上を正しく回答することです。つまり、全問中24問以上を正解すれば合格となります。ただし、この合格ラインは年度により補正されることもあります。
そして、過去のデータを見てみると、第一次検定の平均合格率は66.9%となっています。一方、第二次検定の平均合格率は37.38%と、明らかに第一次検定より低い結果となっています。これから試験を受ける方は、この点を考慮に入れ、十分に対策を練った上で試験に臨むことが推奨されます。(※このデータは土木のみのデータになります)

第一次検定に合格すれば「2級土木施工管理技士補」の資格を取得することができますが、より高いレベルの「2級土木施工管理技士」の資格を取得するためには、第二次検定にも合格する必要があります。そのため、最終的には第二次検定にも合格することを目指し、しっかりとした対策を立てることが求められます。
全体の傾向を見ると、一次検定(令和2年度までは学科)の合格率は大体63%から71%の間で変動しています
(参照:総合資格学院 https://www.shikaku.co.jp/doboku/info/exam/contents/2k_goukaku.html)
2級土木施工管理技士のおすすめ動画
2級土木施工管理技士の試験に合格するためには、過去問を多数解くことや動画で勉強する方法が有効です。ここではおすすめの動画を紹介します。
2級土木施工管理 第二次検定 完全合格のための学習法
https://youtu.be/4ag885HUASA
令和4年度の2級土木施工管理技術検定試験の第二次検定に向けて、過去10年間の第二次検定および実地試験(第二次検定の旧称)に出題された問題の要点を解説。
2級土木施工管理技士「土木一般」~土工~
https://youtu.be/hLVGYQ2ETcw
2023年度(令和5年度)に対応した、2級土木施工管理技士「第1次検定・学科試験」の対策のための動画
まとめ
2級土木施工管理技士の資格は、土木工事の監督や指揮を行うことが可能な国家資格であり、その取得は第一次検定と第二次検定の両方に合格することで可能となります。
平均的な合格率を見ると、第一次検定は66.1%、第二次検定は36.1%となっており、後者の方が合格するのが難しいと言えます。勉強法としては、過去問を反復して学習するのが一般的ですが、動画投稿サイトを使用するなど、新たな学習方法も登場しています。
この資格を取得することで、その人の業務範囲が広がるだけでなく、スキルアップやキャリアアップにもつながります。
さらに、この資格を持つことで、自身が監督や指揮を行った作業が地図上に記録され、人々の生活に欠かせない存在となるという点でも、その価値があります。
この機会に、2級土木施工管理技士を目指してみてはいかがでしょうか。
【あなたの理想の職場探しに】建設業に特化した求人をご紹介!
幅広い職種であなたにあった求人が見つかる!高収入、土日休みの企業も掲載!いますぐ転職を考えていない方も、登録するだけでスカウトメールが届きます。
ご自身の市場価値を確認して、より良いキャリアを作っていきましょう!
※その他、新着求人はこちら。
この記事を書いた人
読んだ記事をシェアする

